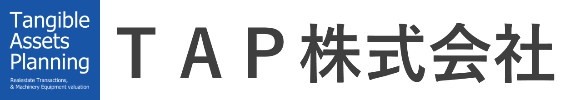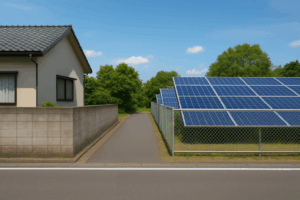最近は、所属する一般社団法人日本資産評価士協会が参加している太陽光発電の格付評価プロジェクトの現地調査を請け負っており、静岡県や愛知県の東部を中心に太陽光発電施設の現地調査に従事しています。
不動産と機械設備のデューデリジェンス的なもので、太陽光発電施設は宅建業の範疇である建物や構築物には当たらないのですが、土地に定着するものではあるため、性質としては構築物に近いものと言えます。
太陽光発電施設は大まかに分けると屋根上にパネルを設置するものと、未利用の土地にパネルを設置する野立てタイプに分類されます。最近は各地で森林を大規模に切り開いたメガソーラーに対する批判が高まっています。メガソーラーは”メガ”の名がついている通り出力1,000kW(1MW)を超える発電施設を言いますが、野立ての施設の数としてはメガソーラーよりずっと規模が小さい、出力50kw以下の”低圧”と呼ばれる発電所の方が多くなっています。
不動産開発の分野では大規模な施設は、周辺環境に与える影響が大きいため、大規模なものは強い規制を受ける傾向があります。太陽光発電施設においてもメガソーラーに対する規制が特に近年は厳しくなっています。一方で、低圧のような小規模施設は比較的規制が緩いのが現状です。こうしたことから、実質はメガソーラーなのに小規模の施設に分割・分譲して規制を逃れるケースも散見されました。
逆に言えば小規模の物でも数が多くなれば環境に与える影響は大きくなりますし、小規模とはいえ発電所が自宅の隣にできると住民の方にとってはあまり気分がいいものではないでしょう。
そうしたことから、小規模の施設でもしっかりと運営されているか、発電所を譲渡することになった時に価値に見合った価格付けができるか、さらに固定価格買取制度が2030年代前半に期限の終了を迎える発電所が大量にあり、売電価格の下落によって放置される発電所が出れば、発電量が減少する懸念もあり、政府としても電力インフラ維持のため長期間持続的に運営できる担い手に施設をシフトさせたい思惑もあります。こうしたことから今後は必要性が高い仕事になっていくと考えられ、実地で調査をしながら有効性の高いものにブラッシュアップしていく取り組みに参加しています。
 実地調査は発電所に出向いて調査するのですが、太陽光発電施設は電力を扱う施設ですから、感電の危険が伴います。このため、調査の際には電気を通さない絶縁手袋や絶縁長靴を着用します。また、パネルを乗せている架台はアルミ製の角材を使っていることが一般的ですが、縁が意外に鋭く、人がぶつかったりすると深い傷を負う危険があります。さらにパネル下に入ると梁などの角材に頭をぶつけてしまうことも珍しくありません。それこそ角材で頭を殴られるのと同じようなものですから、ヘルメットは必ずつけなければなりません。
実地調査は発電所に出向いて調査するのですが、太陽光発電施設は電力を扱う施設ですから、感電の危険が伴います。このため、調査の際には電気を通さない絶縁手袋や絶縁長靴を着用します。また、パネルを乗せている架台はアルミ製の角材を使っていることが一般的ですが、縁が意外に鋭く、人がぶつかったりすると深い傷を負う危険があります。さらにパネル下に入ると梁などの角材に頭をぶつけてしまうことも珍しくありません。それこそ角材で頭を殴られるのと同じようなものですから、ヘルメットは必ずつけなければなりません。
発電所の周囲はフェンスで覆い、人が入れないようにしなければならないのですが、現実には柵がなかったり、ロープを張って簡単に施設に触れられる発電所も存在しているのが現実です。柵がなくて近づけるとしても、危ないですから発電施設に近づいたり触ったりしてはいけません。
ヘルメットや厚いゴムの手袋、長靴、さらにマダニの危険もあるので服は長袖が基本で炎天下で調査することになりますので、夏は非常に厳しい作業になります。実際は真夏はもちろんですが、5月下旬ごろから厳しい環境になり、手袋や長靴の黒いゴムに直射日光が当たると焼けるような熱さになったり、ヘルメットから滴り落ちる汗が記録用紙を濡らして書けなくなったしまったり、熱中症で体調を崩す人もいますので、暑さとの闘いは気が抜けません。