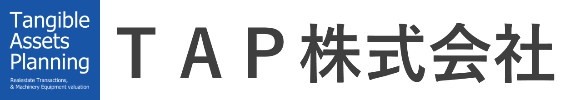最近特にSNSなどでは、太陽光発電施設に対する非難の声が相次いています。
特に大規模なメガソーラーは山林を切り開いたり大きな改変を伴うために、非難の的になっています。
しかし、投稿をよく見ると「メガソーラー」と言えない規模の野立て太陽光発電施設も「メガソーラー」と記載されているものもありますので、メガソーラーに限った話ではないのかなと個人的には思っています。
※メガソーラーはメガワット級の発電能力を持つ施設のことをいい、目安としては敷地面積1ヘクタール=10,000㎡=100m×100mの規模が必要になります。
太陽光発電施設は大きく分けて、敷地上に架台等を設けて直接設置しているもの、建物の屋根の上に設置しているものに分けられます。
建物の上に設置しているものは建物の一部であるため、建築物に当たるのは疑いようがないのですが、土地上に設置されているものは大半が建築物に該当しないことになっています。
建築基準法第2条1号では「建築物」を
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
と定義しています。
太陽光発電施設の多くは架台の上に設置されており、柱は有するものの、屋根や壁に当たるものはないため、通常は建築物に該当しないとされています。したがって、太陽光発電設備そのものの設置に「建築確認申請」は不要ということになります。
建築物としての規制がかからず、建築確認の際に必要とされる構造計算を行う必要もないので、特に事業用太陽光が普及し始めた2012年頃に設置されたものは、単管パイプを組んだだけの簡易な構造のものなどが多く、強風が吹けば飛ばされたり、20~30年にわたる長期間の使用に耐えられないと思われるものも少なくありません。
その他、建築基準法の適用を受けないため、困った問題が起こることもあります。
例えばセットバック。
セットバックと言っても、道路斜線制限、隣地斜線制限などによるセットバックもありますが、問題になるのは道路接面のセットバックです。
道路接面によるセットバックは建築基準法第42条2項に規定する道路に接面する場合に必要になります。建築基準法上の「道路」は原則幅員4m以上必要とされています。一方で建築基準法施行時(昭和25:1950年)以前から存在する幅員4m未満の道路の場合は、特定行政庁が指定すれは、道路とみなされますが、建築物を建てる際には道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線として扱われます。
ここまで書けばお分かりになるかもしれませんが、太陽光発電施設は建築物として扱われないので、この規定が適用されなければ道路後退は必要ないということになります。
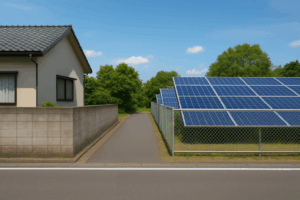
つまり、周囲に建物がある場所に太陽光発電施設が立地した場合、42条2項道路に接面している道路は後退して4m道路を確保しているのに、太陽光発電施設があるとその部分だけ昔の道路幅になってしまう…という現象が起こります。
太陽光発電施設は周囲に外部からの侵入を防ぐためのフェンスを設けることが義務付けられていますので、フェンスで道路の端がブロックされたような見た目になります。
4m道路は普通車がなんとかすれ違えるレベルで、消防車など中型の車両もなんとか入れるくらいの規模感です。4mの接面道路が最低限のスペックとして求められるのには、消防活動など緊急時の安全性確保という理由があります。
発電施設は人が立ち入るものではありませんが、電気を扱う施設であるため、火災のリスクは決して小さくありません。パネルや配線の管理が悪かったり老朽化すれば発火事故はよういにおこりうるものであり、むしろスムースな消火活動を考えるのであれば、広めの道路に接面させることが必要ではないかと考えられます。
太陽光発電施設に関する設置基準は、年々厳しくなっており、当初は発電所の周囲にフェンスが張られていない施設も多数見受けられましたが、最近では少なくなってきています。(発電所の周囲を切れ目なく囲うことが必要で、隣接地のフェンスを利用して一部を省略することも違反となります)
しかし、まだまだ規制が緩い部分も多く、特に周囲の環境に適合することが求められる中では、もう少し踏み込んだ方がいいのではと思うことも現場目線では感じます。